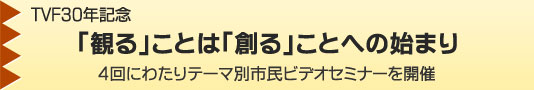アーカイブ情報
1978年から2009年にわたり日本ビクター(株)主催で開催された「東京ビデオフェスティバル」の情報です。

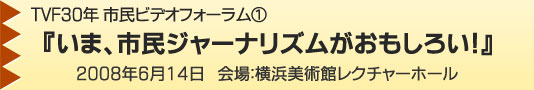

個人の視点、市民の目による暮らしの中にあるジャーナリズムについて、「いま、市民ジャーナリズムがおもしろい!」と題して多彩なゲストを招いてフォーラムを開催しました。
第1部 特別講演
「ビデオジャーナリズムとわが人生」 ゲスト 津野敬子 氏

ビデオジャーナリストであり、DCTVの創設者でもある映像ジャーナリストの先駆者・津野敬子さんに「ビデオジャーナリストとわが人生」という演題で特別講演をしていただきました。講演で話された主な内容は<ビデオカメラ、J.アルパート氏との出会い><DCTVの活動の紹介>で、ニューヨークに本拠地を置くDCTVの活動やポリシーなどがよくわかり、市民ジャーナリズムのあり方が見えてきます。
※特別講演の詳しい内容は、PDFをダウンロードしてご覧いただけます。
TVF30年 市民ビデオフォーラム(1) PDFダウンロード(1MB)
第2部 TVF作品上映&トークフォーラム
「TVF30年の市民ジャーナリズムの軌跡と変遷」

TVF30回の中で寄せられた約5万本という膨大な市民ビデオ作品。その中から、選りすぐった市民ジャーナリズム作品を、TVFの第1回から審査委員として作品を見続けてきた小林はくどう氏が解説しながら19作品をダイジェストで上映しました。
※TVF上映作品&解説の詳しい内容は、PDFをダウンロードしてご覧いただけます。
TVF30年 市民ビデオフォーラム(1) PDFダウンロード(1MB)
【上映作品】
- 「Third Avenue:Only The Strong Survive」
(1980年・アメリカ)
- 「Vietnam:Talking to The People」
(1985年・アメリカ)
- 「走れ!江ノ電」
(1978年・神奈川県川崎市立御幸中学校放送部 神奈川県)
- 「なにかがくるった!〜銀輪公害〜」
(1983年・川崎市立住吉中学校放送部 神奈川県)
- 「ど素人集団のテレビ10年史」
(1985年・千葉ガーデンタウン有線テレビ 千葉県)
- 「緑の都市軸〜豊田大橋建築の記録〜」
(2000年・豊田ビデオリポータークラブ 愛知県)
- 「ダンプ公害〜今、文明の陰で〜」
(1986年・稲葉正央さん 千葉県)
- 「聖域」
(1994年・赤木仁一さん 鹿児島県)
- 「ムラサキウニ物語」
(1995年・鈴木一雄さん 宮城県)
- 「新宿路上TV Vol.3」
(1998年・DROPOUT TV 東京都)
- 「高校生のみた沖縄」
(1997年・ソフト・コム 長野県)
- 「特報 阪神大震災〜半壊マンション理事長の苦悩〜」
(1996年・SSP岩間信生さん 兵庫県)
- 「テレビは何を伝えたか〜松本サリン事件のテレビ報道から〜」
(1998年・長野県松本美須々ヶ丘高校放送部 長野県)
- 「MEETING ANCESTORS(先祖に会う)」
(1994年・ブラジル)
- 「ダムの水は、いらん!」
(2002年・佐藤亮一さん 熊本県)
- 「A Road to Ruin(破壊への道)」
(2002年・イギリス)
- 「Off to War:Chapter Two(いざ、戦争へ 第2章)」
(2005年・アメリカ)
- 「Fear No Evil(災いを恐れるな)」
(2007年・アルゼンチン)
- 「Globalization and The Media(グローバル化とメディア)」
(2003年・イギリス)
- 「レモン」
(2006年・松原 ルマ ユリ アキズキ 兵庫県)
- 「忘れないで」
(2008年・杉並区立東原中学校放送部 東京都)
- 「漢字テストのふしぎ」
(2007年・長野県梓川高等学校放送部 長野県)
トークフォーラム 「いま、市民ジャーナリズムがおもしろい!」

トークフォーラムでは、TVF審査委員3名と津野敬子氏が、活発化しているビデオジャーナリズムについて意見を交わし、現状と未来、そして問題点について検証しました。2時間に及ぶトークの中でゲストスピーカーの各氏は、次のような印象的な意見を述べていました。
大林氏「現代はメディアの数も種類も多様化してきているのに、プロの報道機関はいまだに「人間が犬を噛んだ」ようなニュースばかり報道(中略)市民ビデオと呼ばれる作品が素晴らしいのは「向こう三軒両隣にとっては、犬が人間噛んじゃうことだって大事件ですよね」という、本来の事件が描かれることによって、とても人間らしいやすらぎが得られることだろうと思います」
羽仁氏「良い悪いということではなく、ビデオを撮るという行為を通して市民が市民でありながら、無反省な市民ではなく、見直そうという姿勢を持つことが大切なんだと思います」
佐藤氏「いまの情報社会は情報のリテラシーに欠けているところがあって、どう解釈するかが見る側にゆだねられるところがある。(中略)見る側にゆだねることについて、“これでいいのだろうか”と思えるんです」
津野氏「ジョンは絶対的に反戦の人なのですが、そうした個人のメッセージは言わずに、戦争の現実、若い兵士が負傷して、必死になって助けようとしているドクターがいる事実だけを見せています。彼はその現実を写し出すだけで充分だと思ったんです」
※TVF上映作品&解説の詳しい内容は、PDFをダウンロードしてご覧いただけます。
TVF30年 市民ビデオフォーラム(1) PDFダウンロード(1MB)
【要旨】
- 市民ジャーナリズムにおけるスタイルの変遷
- 市民ジャーナリズムの題材
- ジャーナリズムと市民ビデオの関係
- 戦争と市民ジャーナリズムの関係
- 市民ビデオの意味
【出席者】
- 大林宣彦氏(映画作家、TVF審査委員)
- 羽仁 進氏(映画監督、TVF審査委員)
- 佐藤博昭氏(ビデオ作家・日本工学院専門学校講師、TVF審査委員)
- 津野敬子氏(ビデオジャーナリスト)
- 司会進行・小林はくどう氏(ビデオ作家・成安造形大学教授、TVF審査委員)
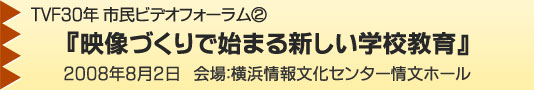

小・中・高の教育現場で、子ども達の手で映像作品を制作する取り組みに注目が集まっています。映像づくりは“グループで取り組み”、自分の役割をきちんと果たしながら制作の過程で持ち上がる数々の問題に対して、乗り越えるための努力が求められます。今回のフォーラムでは、制作の過程で様々な学習効果を内包している映像づくりの魅力について事例を確認しました。
第1部 特別講演
「総合学習と映像づくりのすすめ方」 ゲスト 寺脇 研 氏

学校教育における総合学習の第一人者である寺脇 研 氏が「総合学習と映像づくりのすすめ方」というテーマで講演をしました。その中で映像教育の効果について「つくり方を教えるだけでなく、チームで何かをつくる経験だったり、お互いの作品を見て批評し合うなかでのリテラシー能力だったり、コミュニケーション能力などを養うことだったりします‥‥」。文部科学省大臣官房審議官を務められた寺脇氏に、将来を担う子どもたちに対する健全な育成と、映像づくりを通じた学び方・学習のあり方についてお話をいただきました。
※特別講演の詳しい内容は、PDFをダウンロードしてご覧いただけます。
TVF30年 市民ビデオフォーラム(2) PDFダウンロード(2MB)
第2部 TVF作品上映
「TVF作品にみる映像制作と教育成果・課題」 語りと進行 佐藤博昭 氏

TVF作品には、子どもたちが映像を使って行った数々の学習の成果が残されています。そこには学校生活や行事の記録はもとより、近年では学校ジャーナリズムやメディアリテラシーといった新しい捉え方の作品も増えています。
この第2部では、TVFの審査委員でもある佐藤博昭氏に、映像制作によって実現される新しい時代に即した学習効果や、同時に顕在化する問題点、課題、それらをどう考えていけば良いかを具体的に解説していただきました。
※TVF作品上映の詳しい内容は、PDFをダウンロードしてご覧いただけます。
TVF30年 市民ビデオフォーラム(2) PDFダウンロード(2MB)
【上映作品】

- 『龍胆(りんどう)』
(第26回・長野県須坂高等学校放送委員会 長野県)
- 『ブラックアイ〜花たちの宇宙〜』
(第26回・青森県立三本木農業高等学校放送部 青森県)
- 『忘れないで』
(第30回・杉並区立東原中学校放送部 東京都)
- 『足・ウラ事情』
(第30回・昭和女子大学附属昭和中学校放送部 東京都)
- 『走れ!江ノ電』
(第1回・川崎市立御幸中学校放送部 神奈川県)
- 『里山カエル図鑑』
(第30回・姫路市立菅野中学校生物・理科研究班 兵庫県)
- 『映像詩 曽根干潟から』
(第30回・北九州市立曽根中学校視覚聴覚放送部 福岡県)
- 『逆上がりできないの 何でだろう?』
(第26回・石津善久さん 愛媛県)
- 『学園西遊記』
(第30回・京都市立下鴨中学校パソコン部 京都府)
- 『A Bridge Over the Ocean』
(第10回・細見勝典さん・原勤さん/Douna Boyntonさん 神奈川県)
- 『ビデオ家庭訪問』
(第11回・山本清志さん 愛知県)
- 『心のふるさと』
(第25回・山本清志さん 愛知県)
- 『メディアと共に』
(第22回・長野県松本美須々ヶ丘高等学校放送部 長野県)
- 『漢字テストのふしぎ』
(第29回・長野県梓川高等学校放送部 長野県)
- 『学びの場が消えてゆく〜夜間高校の教室から〜』
(第30回・斉藤雅之さん 神奈川県)
- 『高校生のみた沖縄』
(第19回・ソフト・コム 長野県)
- 『なにかがくるった!〜銀輪公害〜』
(第6回・川崎市立住吉中学校放送部 神奈川県)
- 『1日』
(第25回・兵庫県立伊丹北高等学校放送委員会 兵庫県)
- 『ミジンコピンピン』
(第27回年・日本大学藤沢高等学校放送委員会 神奈川県)
- 『見えない危機』
(第29回・板橋区立志村第二中学校総合科学部 東京都)
- 『5 Senses Travelers』
(第26回・神奈川県立弥栄東・弥栄西高等学校(当時) 神奈川県)
- 『パパは彦レンジャー』
(第28回・本町1丁目商店街振興組合 熊本県)
- 『レモン』
(第28回・松原ルマ ユリ アキズキさん 兵庫県)
第3部 事例紹介
「学校現場における映像づくりの実例紹介」 進行・コーディネーター/下村健一 氏

映像づくりは、総合学習だけでなく国語科、社会科などの教科にもユニークな試みが実際に行われています。今回は、各地から成果としてあがってきた多くの事例の中から、学校現場で実際に携わってこられた先生や関係者をゲストスピーカーとしてお招きし、実施の内容とその効果について紹介していただきました。進行・コーディネーターには、マス・メディアや市民メディアを熟知している下村健一氏。各ゲストが発表を終えると、ポイントとなる部分への鋭い質問や確認により、各事例のポイントをしっかりと押さえていただきました。
※事例紹介の詳しい内容は、PDFをダウンロードしてご覧いただけます。
TVF30年 市民ビデオフォーラム(2) PDFダウンロード(2MB)
【発表事例】
- 映像を使った総合学習とまちづくりとの融合
〈神奈川県横浜市立滝頭小学校/まちの元気づくり支援拠点「夢たま」〉
- 総合学習をきっかけとした映像制作と部活動の展開
〈東京都杉並区立東原中学校〉
- 地域環境問題に取り組む子どもたちの映像制作活動
〈福岡県北九州市立曽根中学校〉
- 地域の問題を映像を通して探求する市民ジャーナリズム
〈長野県大町北高等学校〉
- 美術コースの必須科目となった映像メディア表現の新たな展開
〈神奈川県立弥栄高等学校〉
- 公共広告の手法を使った映像表現と官学協働活動
〈滋賀県成安造形大学〉
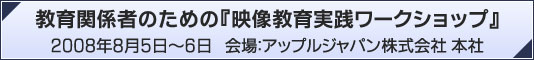
「映像づくりを授業に取り入れるための実務がわかる」と銘打って、先生方や教育関係者のみなさんを対象に映像教育の初級実践ワークショップを行いました。映像づくりを1から学び、機材を使った撮影・編集の実習、そして上映会まで2日間のプログラムで映像づくりに取り組みました。(受講者:30名)
ワークショップスケジュール
| <1日目> |
- レクチャー1 映像教育の目的と実践例
(東京ビデオフェスティバル(TVF)作品から学ぶ)
- レクチャー2 映像制作の基本
- レクチャー3 教育現場での映像制作について
- グループワーク開始 使用機材の概要説明
- 課題詳細説明 デスクワーク作業手順
|
| <2日目> |
- グループワーク 撮影
- 撮影済み映像の確認〜編集システム説明
- 各グループ編集作業
- 作品完成〜各グループ作品を鑑賞・講評
|
※使用機材 ビデオカメラ/ビクターEverio、パソコン/アップルMacBook Pro
ワークショップフォトギャラリー
●レクチャーの様子
講師の佐藤博昭氏から、映像づくりを教育現場で行うことの狙いや効果について説明。TVFに寄せられた生徒や先生たちが手がけた映像作品が紹介されました。その後、五嶋正治氏(東海大学文学部広報メディア学科准教授)から、教育現場における映像制作の実際についてお話が披露されました。
●グループワーク<絵コンテづくり>
作品づくりのために絵コンテの作成からスタート。課題は人物紹介です。グループ分けされたメンバーをお互いに紹介しあうもので、アイデア出し合いながら絵コンテの作成に取り組みました。ここからの制作では、お手伝いするサポートスタッフも配置され、疑問や手法について的確なアドバイスが送られていました。
●グループワーク<撮影>
2日目は、昨日、制作した絵コンテに沿って、グループごとの撮影です。各グループにハードディスクムービーEverioが渡され、様々な場所で和やかながら真剣に撮影が繰り広げられました。
●グループワーク<編集>
午前中に撮影を終え、午後からはいよいよ映像の編集。パソコンはアップルのMacBook Pro。ビデオ撮影の経験はあっても、編集経験となるとほんのわずかしかいなかった参加者。心配されましたが、説明を聞いてから編集作業が始まると、むしろ「映像に変化をつけたい」「静止画を使いたい」「アフレコしたい」など、映像表現と編集の楽しさにのめり込み、作品づくりに没頭していました。
●作品完成・鑑賞会
3時間弱という短時間ながらも編集を完了。いよいよグループごとに上映です。今回のワークショップで集まり初対面だった参加者も、「人物紹介」という課題制作を通して打ち解けあいました。最後にワークショップ参加の感想を各人が発表し、この2日間で経験した映像作品づくりの楽しさ、協力しあうことで成し遂げられる達成感とその重要性について実感し、教育現場に戻ってからこの経験を生かしたいと述べていました。総評として佐藤博昭氏から「学校現場で実践する場合は、今日の楽しかった気持ちを思い出し、指導するというよりも一緒に映像づくりを楽しむという気持ちで実施していただきたい」。また、五嶋正治氏も「人をはずかしめてしまう側面もあるカメラと映像メディアのリテラシーも教えることも大切。それは完成した作品を一緒に観て感想を述べ、評価しあうことから学べます」——と述べ、締めくくりました。
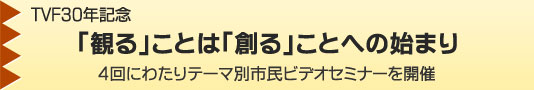
TVF30年にわたる入賞作品の中から、作品を選んでじっくり分析・解説する「市民ビデオセミナー」。5月の開催を皮切りに、テーマごとに4回にわたって開催し、多くの来場者にお集まりいただきました。
『自己』を描く 2008年5月17日開催
ゲスト 荒井純子さん(「古希 ひとり旅」作者・TVF2008)
ゲスト 保立友司さん(「ぼくのまわりで起きたこと」作者・TVF2002)

自分を描くためには、内面にある心模様と自分らしさを表現する方法を知る必要があります。TVF入賞作品を通して、その方法が披露されました。(受講者:19名)
『人』を描く 2008年6月21日開催
ゲスト 金子豊一さん(「サルマータの夢」作者・TVF2002)
ゲスト 藤井善郎さん(「田舎暮らしの真実は」作者・TVF2008)

自分(制作者)と被写体との心の距離を近づけ、被写体の思いを知ることができたときに記録された映像が作品化へと大きく前進。ゲストのそんな体験談が参考になりました。(受講者:22名)
『社会』を描く1 2008年7月19日開催
ゲスト 国本隆史さん(「駅舎に登ろう」作者・TVF2008)
ゲスト 斉藤雅之さん(「学びの場が消えてゆく」作者・TVF2008)

地域や伝統、教育、格差について取り上げました。作者の問題意識が、多くの人へ向けて発せられるメッセージ。市民ジャーナリズムと言われる作品の数々に、多くのことを気付かせられました。(受講者:19名)
『社会』を描く2 2008年9月20日開催
ゲスト 内田リツ子さん(「共働き」作者・TVF2007)
ゲスト 滝澤厚子さん(「ねえ、ママ聴いてるの?」作者・TVF2004)

環境や観察、子育て、仕事について取り上げました。目の前で繰り広げられる出来事を克明に描写・記録し、伝えたいことを表現することに作品づくりおもしろさを感じました。(受講者:16名)
市民ビデオセミナーは作品づくりの視点を養います。
市民の問題意識が映像作品となって結実しているのが市民ビデオです。日常の暮らしの中にある出来事について、そこに暮らす人の視点でまとめた作品であり、マスメディアでは取り上げられないような題材も丹念に作品として残されており、それらが数多く集められているのがTVFでもあります。
市民ビデオセミナーは、TVFの審査委員である佐藤博昭氏を講師に、身の回りの現象に眼を向ける視点を養い、作品化までの考え方を学ぶ場です。これまで、TVFに寄せられた作品を参考にしながら、題材の見つけ方や構成などについて解説が受けられます。毎回、TVF入賞者の方をゲストにお招きして、ノウハウの披露もあります。次回、開催の折は、ぜひ、ご来場ください。