アーカイブ情報
1978年から2009年にわたり日本ビクター(株)主催で開催された「東京ビデオフェスティバル」の情報です。
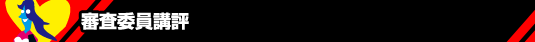
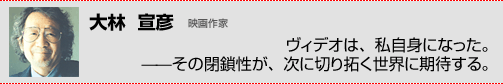
《やもめ男の物語り
》という77才ヴェテランの男性のドキュメンタリー。被写体の若い女性と擬似恋愛の契約を結ぶ。正直な人だと思った。カメラを手にすれば、人は必ずやその被写体と恋をする。擬似であり、ウソであるからこそ、ウソから出たマコトを生む。ドラマもドキュメンタリーも、こういう虚実の皮膜から生まれる。一見変な老人がカメラを持つのをよいことに若い娘を追いまわす。アルフレッド・ヒッチコック氏も小津安二郎先輩もこうやって名作をものして来た。ヴィデオは今、そういう創作の秘密を自覚し始めたんだなあ!それも市井の人びとの日常の中で。これはヴィデオの一つの達成だと思う。危険もウチに潜んでいるが、その尖った切っ先が、現代の人間社会に潜む危険を暴き出しもする。若い作家たちが突出して来たのも、そういうヴィデオなるものへの自覚からだろう。
《初夏の日
》の持つ日常性への関わり方は、文学、音楽の世界で彼らが発見して来たマコトを映像世界で柔軟に表現し始めた大きなうねりの一つだ。彼らは《
やもめ男の物語り
》の被写体にされちまった自分を、世界に対して問い掛け始めている。それが《
ホウムルーム
》や《
いまどきの21歳の主張
》に誠実に辿りつき、《
青空夜空に星空
》のようないまどきの大傑作メルヘンに結実し、印度を東京の日常の倶楽部に仕立て、自らのアイデンティティー、すなわち“正体”と成す。《
ホウムルーム
》のようにトイレまでを擬似恋愛の日常と化す。「世界は元もと全幅の信頼を寄せる場所」であった中学生たちが、それを疑い考え始める力を持った。親も学校も友人もそういう視点から見直し始める。危険だし悲しいが、世界とはそういうものであり、そこから人間を考え直してみることが必要な時代なのである。見つめ、考えることの中から、希望もまた発見されるだろう。人間は考える生命だから。《
やもめ男の物語り
》の被写体たる被害者の若い女性もまた愛を持ち得るか? ぼくらは今、誰もがこの社会における被写体たる奴隷でもあるのだ。ヴィデオは今、“私ヴィデオ”の視点を持つことで、世界を、人間なるものを考え直そうとし始めている。映す、ということは、好きだよ、と言い切れることなのか。「感動の麻痺」は救い得るのか。《
59年ぶりの「再会」
》は、そこの所をこそ問いかけているのであるだろう。
TVFは世界唯一のビデオの祭典だ。今回は30回を迎えた記念すべき年である。これまでに色々あったが、TVFが東京から発信し、世界中に広がり、多くの支持を得て続いて来た理由に、ビデオを通じて地球家族を実現しようとした先見性と日本ビクターの組織力が挙げられる。TVメディアの発達に伴い、偏った報道は地球は小さく、画一化、均一化している。これに対してTVFは市民のローカルな文化がぎっしり詰まった地球の大きな広がりを表現している。アジアからの参加点数が増え 、人々の生き生きした生活の中に、都会と田舎の格差やコミュニティ、家族の崩壊などの市民の目線が込められているのは興味深い。
私にとってTVFはビデオを通して社会を学ぶ場でもある。大賞『最終章
』は国際結婚をした『私』という自我を軸に家族論が展開され、ディスコミュニケーションの関係であった父親との断絶のエピソードは背景にある受けた教育の違いが次第に浮き彫りになってくる。
大賞『いまどきの21歳の主張
』は若い女性感覚の日記自画像だ。前のめりで大阪お喋りの映像文体が新鮮だ。
今回も大賞が2つ出てしまったが、ベスト1を選ぶために審査をしているのではない。TVFは『ビデオのジャングルだ』とあえて言いたい。ジャングルには様々な種類の植物、バクテリア、昆虫、野生動物が共生している不思議さがある。そこには強者も弱者もない。どんなに乾季も雨季が続こうともそれぞれが支えあって生きている。全作品が一堂に視聴できる映像のジャングルを観客がさまようイメージが浮かんでくる。でも現実に実施するのは困難だ。審査をすることは毎年、TVFのジャングルの中から社会や時代を象徴する様々な力作を見出しているのだと自負する。グランプリはその代表である。今回は《自画像》《家族》《コミュニティ》《教育》をモチーフにした作品が多い。私が他に押したのはコンビニの常連たちがつくるコミュニティ『店主
』、中学生たちによるハンセン病に対する社会の眼を追及した『
忘れないで
』、家族が帰省しない老婆たちの孤独にスポットを当てた『
銅門日記
』、哲学的物語のクレイ・アニメ『
蒲公英の姉
』である。
今年のエントリー作品を確認し、最終審査会を終えた今、改めてTVFとは何かを考えている。例年以上に、そもそも作品の総評を試みること自体が後ろめたい。そう思わせるような、作品の幅と作者の広がりが30年を経たTVFなのだなと思う。TVF作品に接する自分なりの作法がある。まずは目の前に現れる作品に可能な限り無垢な気持ちで向かい合うこと。これまでの知識や経験は取りあえず後方に置いて静かに身を委ねる。そして作品を見終えた時、この作品を誰かともう一度見たいかどうかを自問する。この体験を共有できる誰かを心中で捜している。具体的には学生達であったり、セミナーで出会った人達だったりする。作品がより多くの人達の目に触れるように願い、この審査会がその為の手続きであればいいと思っている。僕が推薦した作品はこの「共有」を基準にしている。それらが今年の優秀作品としてふさわしいかどうかはTVFという審査委員長が判断する。TVFらしさを主張するのは30歳のTVFそのものだと改めて思った。
個人的には『Ladenhüer(店主)』の素敵な映画的空間に嫉妬していた。審査会の後、昨年の『2 minuten(2分間)』の作者だとスタッフから教えられ、あの極めてビデオ的なポートレイトを作った24歳の作者だとは想像が出来なかった。何処にでもあるような、冴えない店の店主と毎日やってくる冴えない常連客、何も変わらない毎日。小さな事件とまた繰り返される日常。こんな空間を魅力的に描ける作者が羨ましい。また、『
描写の記録:時間の足跡
』のあきれるほどの労力に感動した。作者は作品が出来上がることを本当に確信していたのだろうかと、制作現場で繰り返されたであろう引きこもりのような日常を想像した。『
最終章
』をはじめ、TVFが判断した今年の象徴的作品はどれも素晴らしい。様々な年齢の作者が、それぞれの環境で制作した作品が、30年を経てなお「市民ビデオ」の次の局面を予見させる。今年も豊かな経験をさせてくれた世界中の作者に感謝する。
中高年と二十歳未満の学生、わかい女性、の作品群が目立った。壮年世代は仕事が忙しくなかなかまとまった作品に挑めないのかもしれない。けれどいまや幼稚園や小学校の運動会は親たちのビデオカメラの砲列になる、というから機材を持っている人は多い筈だ。なにか作品にするテーマとモチーフがないのかもしれない。
中高年の作品には時間をかけた労作。わかい女性の作品には才能を感じた。日本に映像現場の状況といったらいまや機材は優秀だし、撮影タブー地帯は少ないし(よその国に比べて)まさに豊穣の映像時代にあるような気がするが、のけぞるような傑作はなかった。無意味な十六対九のアスペクト。多機能表現の使いすぎ(特殊なワイプなど)撮影機材のてんこもりサービス機能にふりまわされている印象もあった。外国作品はプロパガンダ系と純粋芸術系にわかれてきたが、例年とあまり変わらなかった。今回は「最終章
」と「
いまどきの21歳の主張
」の二本でキマリと思って選考委員会に望んだがそのとおりになってしまった。
今年も作品の多様さは見事と言うほかなく、これこそがTVFの魅力なのだと思う。しかし同時に、作品の評価をどういう観点・基準で行うかが極端に難しい。その観点・基準もまた、多様にならざるをえないからだ。優秀作品賞を三〇本にしぼることは審査員にとって酷であり、今年も幾多の秀作が入賞から洩れた。そのうち、「フォードのある村
」と「
ひとすじの道
」に一言。全く別種の作品だが、ともに丁寧に写し出されるのは人間ではなく、モノが中心。フォードという浅瀬と豆腐製造機。そのくせ、心地よくまた力強く、自然・文化・文明をめぐる人間の営みに対する深い感慨を呼び起こさせずにはおかない力がある。佳作の中に傑作があり、逆に、入賞作にただちに共感できなくても不思議はない。それこそが多様性の証しだから。
身辺雑記や偶感を気軽に綴るように、ビデオを撮りコメントする。たとえ格調や形式感がなくても、その個人の率直な心情がビデオならではの「あり方」で立ち現れる。ときにはその手法を意識的に使ってセミ・フィクションをつくる。そんな作品のもつ「個人性」、その表現の可能性に審査会は注目してきた。大賞の一本に「いまどきの21歳の主張
」が選ばれたのもその現れである。ただ、過去の同傾向の大賞作とくらべ、トーンダウンしたことは否めないと思う。
もうひとつの大賞「最終章
」は、内容・表現とも、あらゆる点で文句なしの受賞。日本ビクター大賞「
学びの場が消えてゆく
」もまた、夜間高校消滅という切実で緊急を要する問題を扱いながら、それがそのまま「学校に何が必要か」という問いかけへの具体的な回答を示唆していて見事である。
いつもながら誠実・堅実・また簡潔な作品には敬意を表したいが、アニメーション作品が今回少なかったこと、昨年の「漢字テストのふしぎ」のような、着眼点・問題性・撮り方・人間観察・完成度のすべての面で新鮮かつ驚嘆すべき作品がなかったことは少し残念だ。
新しい根が、しっかりと根づき、方々に伸びている。そんな感じがとても楽しかった。
まず第一に、ビデオを作られる御一人、一人が、“自分の眼”で見て、“自分の心”で感じている作品が多くなった。さらに、その背後に“自分の生活”がしっかり存在している。そんな作品がふえてきた。今年は、中学生諸君のビデオに、すぐれたものが多かった。学校やその周辺を描くものもあったが、もう少し広い世界に踏み出した作品もあった。その見方が、“自分の眼”を大切にしているのが、普通の新聞やテレビの記者さん達とはちがって、面白い。「授業
」「
忘れないで
」「
曽根干潟から
」「
足・ウラ事情
」などが印象に残る。
もう少し年上の人達が、自分の心を見つめる作品も、今年は拡がった。「いまどきの21歳の主張
」「
ホウムルーム
」とても良かった。年配の作者達が生活をみつめる眼にも、個性が感じられる。「
最終章
」はみごとだったし、「
畑へ
」「
田舎暮らしの真実は
」「
ごみ収集顛末機
」それぞれに重味がある。
作品としては、「蒲公英の姉
」にいちばん感服した。この若い作者は、期待のアーチストとしての未来がとても楽しみだ。TVFの大きな流れとは少し異質かと思って、グランプリには推さなかったが、未だ心の中では迷っている。とにかく幻妙な美しさに溢れた傑作である。「
店主
」も素晴らしかった。これは暗黒喜劇の傑作だが、二十一世紀の世相にもあまりに見事な諷刺ともなっている。「
互 LINK
」の鮮烈なイメージも忘れ難い。「
描写の記録
」のアニメーションにも驚いた。乏しい色彩が豊かなイメージを作りだし、消失しそうな「時間」の記憶の断片が奇妙に美しい。「
漂流
」も、青年の夢幻が、いつのまにか文章を書くことよりは、日常の破片の中に吸いこまれていくところが魅力的だった。
30年を迎えたTVF。家庭用ビデオVHSの発売と共に始まったTVFは、参加者の創意と審査委員の先生の熱意によって支えられてきた。累計5万タイトルを送って頂いた一人ひとりの参加者の皆様に、心から御礼を申し上げたい。
昨年『漢字テストのふしぎ』でビデオ大賞を受賞した長野県梓川高校の林先生が進められているメディアリテラシー教育が、多くの学校で同じ様に実践されている事を実感すると共に、明日への心強さを多くの作品の中に感じる事が出来た。
今年の作品『忘れないで
』は、杉並区立東原中学校放送部が作ったハンセン病患者に対する虐待と偏見の歴史に対する「私達の主張」を見事に描き出した。作り手と受け手を往復しながら、人々の共感を順々に積み重ねていく。人の為に、熱い想いを持つ事の出来る若い世代は、未来への「希望」「愛」「楽観」を感じさせてくれる。
家族と自分との関係をテーマとした作品の中で、『The Last Chapter (最終章)
』と『
59年ぶりの「再会」
』の2作品が光った。この2作品には「家族とは何か」を考えさせてくれ、周囲との多くの語り合いが生まれた。自分の父を見つめる『
最終章
』、母が6歳の時に別れた父への想いを追いかける『
59年ぶりの「再会」
』。
似たテーマであるにも拘わらず、全く違う作品が誕生した。TVF2008で、この2作品に出会えた事は、本当に幸せだった。完成度では『最終章
』、荒削りながらも『
59年ぶりの「再会」
』は連綿と続く家族の愛をスケール大きく表現した作品として、共に大いに評価したい。
『学びの場が消えてゆく
』は、まさに個人ジャーナリズムの視点を見せる。ありのままを受け入れてくれる夜間高校。様々な個性と背景を背負った人々を軸に、教育の在り方を見つめ直す。
毎年新境地を感じさせてくれるTVF。参加者の「創る悦び」が、「観る楽しみ」と「語り合う歓び」を、TVF2009に運んでくれる事を期待したい。